たけのこ堂鍼灸院たけのこどうしんきゅういん
-
せんねん灸セルフケアサポーター柴田 千恵
-
- JR新検見川駅もしくは京成八千代台駅から京成バスに乗り、鉄工団地入口で下車し、徒歩10分
- 千葉県千葉市花見川区千種町143-17
- カテゴリー シニア/妊活/ビューティー/ランナー/肩こり/腰痛/ひざ痛/冷え/しびれ/目の疲れ/不眠/むくみ/不妊/美容
・お問い合わせ090-8727-3548
・お問い合わせ090-8727-3548

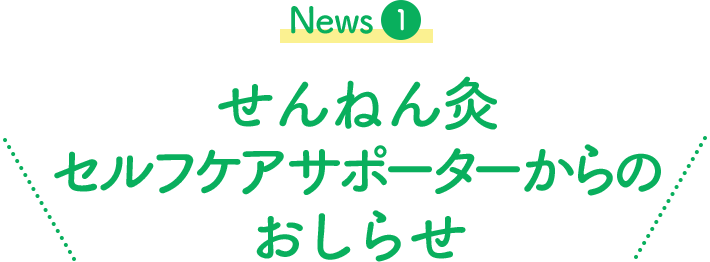
【心と身体の関係】
☆肝臓←悪化→怒りっぽい・頑固・威張る・見栄張り・肩書に弱い
☆心臓←悪化→冷たい・関りを嫌う・厳しい・気難しい
☆消化器←悪化→落ち込む・怠惰・能天気・優柔不断・八方美人
☆肺・大腸←悪化→泣き虫・計算高い・諦めやすい・悲観的・厭世的
☆腎臓←悪化→怖がり・意欲がない・根気がない・心配性
冷え取りで内臓の毒を出しながら自分でも性格(思い)を変えるように努力をします。病気(内臓)が良くなってくると、それに伴う感情や思い、性格も徐々に穏やかになってきます。そして、ある程度元気になった時には、自分の欲のためではなく、自分の能力をできる限り使って、周囲(人や物や自然など)の役に立つような「他人本位」な生き方を目指していきましょう!
怒りは自分の思い通りにならない自分本位の思いが原因で起きる感情ですが、これがいつものことであれば、怒りっぽい性格になってきます。自分の性格は、長年に渡ってどのような思いで生きてきたか?ということに基づいて出来上がっていることが多いため、自分の性格を客観的に分析することは、自分を振り返る良い方法です。自分の思い(欲)と、これによって起きる感情、そして、それが積み重なって出来てくる性格、この3つは互いに影響し合っているからです。つまり、欲を減らせば性格も変わり、健康にもなれます。
また、自分の病気によって「心の毒」を作ってしまう場合もあります。心と身体は密接に関わっていますので、内臓に病気があると、その内臓と繋がっている感情が乱れ、思いも自己中心的なものに偏っていきます。これが原因で「心の毒」が作られ、この毒で内臓も悪化するという悪循環に陥ってしまいます。
☆自分本位を改めること
例えば、お金や名誉、物への執着を始め、楽をしたい!病気を早く治したい!という思いや家族や友人や会社などへの思いは人によって異なります。誰もが自分の思い通りに生きようとすれば、当然、摩擦が起き、ぶつかることが多くなります。そして、互いにギクシャクした生活を送ることになった場合、誰もがストレスを溜め、次第に病気になっていきます。
つまり、「自分本位」の生き方は、社会生活の中では成り立たないということです。これを無理に通そうとすれば、思い通りにならないということで、自分の心に毒が溜まるだけではなく、周りの人も同じように毒が溜まっていきます。たとえ、それが真に相手の為だと思っていることであっても同じことです。
例えば、病気で苦しんでいる人に冷え取りを勧めようとしても、その人に受け入れる気持ちがなければ、気持ちの負担を強いることになります。勧めた人も勧められた人も、互いにストレスを溜めてしまう結果になります。
ストレスを溜めないためには、まず、自分をいつも振り返り、自分本位の思いに気付くことが大切です。それには、自分自身を色々な角度から見るように心がける必要があります。
☆自分本位を改めること
冷え取り健康法は「鍼灸治療」「靴下の重ね履き」「半身浴」「食べ過ぎを止める」ことだけだと思っている人が多いと思います。確かにこれを実行すると身体は「頭寒足熱」の状態になり、身体の自然治癒力は高まりますので、病気の元である冷え(毒)をたくさん排出することができます。これを続けていると様々な症状は徐々に軽くなり、そして消失していきます。
しかし、排毒している一方で、それ以上にたくさんの毒を自分自身が作り出してしまっているということも実際に起きています。自分で作る毒とは、ほとんどがストレスや感情の乱れなどによって溜まる毒、つまり「心の毒」です。「心の毒」が症状という目に見える形で出てくるときは、5000倍にもなると言われています。これでは鍼灸治療に通っても、半身浴を何時間行っても毒は出し切れないとう事態になってしまいます。
そうならないためには、できるだけ「心の毒」を溜めない生活を心がける必要があります。「心の毒」の根源を探っていくと、それは「自分本位」の思いに至ります。「自分本位」とは「自分の思い通りになって欲しい!」という「欲」のことです。
中国の「漢書」列伝には、出産を扱う「乳医」という職業が記されています。現代でいえば、女医・助産師に相当します。
その後、漢の時代には、インドの仏教経典から看護の精神が伝わり、唐の時代には、寺院に付属した仏教の救療慈善施設である「病坊」で、僧尼による看護が行われました。これは仏救看護の先駆けでした。
しかし、それ以降は、国家的な医書が編纂され、病院や診療施設がつくられ、仏教から儒教へと宗教も変わっていく中で、中国における古代崇拝、男尊女卑などの理由により、看護という職業は歴史上の表舞台に現れなくなります。
朝鮮の看護は、李朝時代、「医女」という制度がありました。医女とは、看護師、助産師、下級医師としての、東洋で初めての看護職です。このうち「内医女」は下級医師としての診断、調剤、施術(鍼灸)をしることができました。近年では。韓国ドラマなどでもたびたび内医女が登場し、日本でも知られるようになりました。

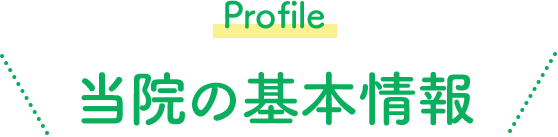
鍼灸院名
たけのこ堂鍼灸院
平成21年4月開業

せんねん灸セルフケアサポーター
柴田 千恵しばた ちえ
~ 学歴 ~
法政大学文学部史学科卒業
関東鍼灸専門学校卒業
東京衛生学園臨床教育専攻科卒業
~ 職歴 ~
三和銀行(現東京三菱UFJ)
ホンダプリモ京葉(経理課)
千葉スバル自動車(保険課)
関東鍼灸専門学校
お子様からご年配の方まで「体の悩み」なんでもご相談ください。
お気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
| 鍼灸院名 | たけのこ堂鍼灸院 (たけのこどうしんきゅういん) |
|---|---|
| 住所 | 〒262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町143-17 Google マップで見る |
| アクセス | JR新検見川駅もしくは京成八千代台駅から京成バスに乗り、鉄工団地入口で下車し、徒歩10分 |
| TEL | 090-8727-3548 |
| 営業時間 | 随時受付 |
| 定休日 | お問い合わせください |
| ご予約 |
090-8727-3548 フォームで予約 |
| 施術内容 | はり・灸 |
| 料金 | お問い合わせください |
| カテゴリー | シニア、妊活、ビューティー、ランナー、肩こり、腰痛、ひざ痛、冷え、しびれ、目の疲れ、不眠、むくみ、不妊、美容 |
| メールアドレス | takenoko33chie0618@yahoo.co.jp |